退職後は、健康保険や年金の手続きだけでなく「税金」関係の対応も必要です。
この記事では、住民税・所得税・年末調整・確定申告について、分かりやすく解説します。
☆退職後に必要な税金手続きとは?
退職後に関係してくる税金は主に以下の4つです。
- ・住民税
- ・所得税(源泉徴収)
- ・年末調整 or 確定申告
- ・雇用保険に関する課税の確認(非課税ですが念のため)
①住民税について
住民税は前年の所得に基づいて課税される
住民税は「前年の所得」に基づいて課税されます。
例えば、2025年に支払う住民税は 2024年1月~12月の収入 に対して課税される仕組みです。
そのため、退職した年に収入がなくても、前年に給与があれば翌年も住民税の支払いが必要になります。
会社を辞めた後の支払い方法は?
退職後の住民税の支払い方法は以下の2通りです。
- ・一括徴収(退職時に清算)
退職時に、残りの住民税を給与や退職金からまとめて支払う方法です。
・会社に依頼して「一括徴収」してもらうケースが多いです。
・手続きが完了すれば、退職後の納付手続きは不要になります。
- ・普通徴収(市区町村から納付書が届き、自分で支払う)
会社で一括精算しなかった場合は、退職後に自宅へ納付書が届きます。
・年4回に分けて支払うのが基本です(6月、8月、10月、翌年1月)。
・金融機関やコンビニ、自治体のオンライン決済などで納付可能です。
☆会社を退職する際に、どちらで支払うか選べる場合があるので、人事担当に確認しておきましょう。
退職月によって変わる支払いタイミング
住民税の支払い方法は、退職の時期によっても異なります。
- 1月~5月に退職
→ その年の6月以降の住民税は、納付書で支払うことになります。 - 6月~12月に退職
→ 残りの住民税を退職時に一括で精算するか、納付書で分割納付するかを選択できます。
退職後の住民税で注意したいポイント
前年の収入が多いと、無職でも支払い額が大きくなることがあります。
失業中で収入がない場合でも、住民税は必ず請求されます。
経済的に厳しい場合は、自治体に「減免制度」や「納税猶予制度」があるか相談してみましょう。
まとめ|住民税は退職後もついてくる!
退職後は健康保険や年金の手続きに目がいきがちですが、住民税の支払いも忘れないようにしましょう。
「前年の収入に対して課税される」という仕組みを理解しておくと、支払いに備えやすくなります。もし負担が重いと感じたら、早めに自治体へ相談するのがおすすめです。
②所得税の扱い
源泉徴収で天引きされている
会社員として働いている間は、給与から所得税が毎月自動的に差し引かれています。これを 源泉徴収 といいます。
退職した月の給与や退職金からも、所得税は天引きされる仕組みです。
つまり、退職するまでの所得に対しては、基本的に会社が源泉徴収で処理してくれています。
退職金と源泉徴収
退職金が支給される場合も、原則として会社が所得税を源泉徴収します。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、本来より多く税金が引かれてしまうため注意が必要です。提出していないと、一律で20.42%(所得税+復興特別所得税)が天引きされてしまい、本来より多く税金を払うことになります。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除は、勤続年数に応じて次のように計算されます。
- ・勤続年数20年以下:
40万円 × 勤続年数 (最低80万円) - ・勤続年数20年超:
800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
☆例:勤続25年の場合
800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円 が非課税枠になります。
退職所得の課税方法
退職所得の課税額は次のように計算されます。
- ①退職金 − 退職所得控除額
- ②その金額を 1/2 にする
- ③所得税率をかけて税額を計算
つまり、控除後の金額をさらに半分にしてから税率をかけるため、通常の給与よりも税負担がかなり軽くなるのです。
退職所得の受給に関する申告書について
・退職金を支払う会社から配布されます。(自分で国税庁のホームページからダウンロードすることも可能)
・提出すれば「退職所得控除」が適用され、税金が大幅に軽減
・提出しないと一律20%課税されてしまい、後で確定申告が必要
◎提出先:退職する会社
◎提出のタイミング:退職金を受け取る前
◎記入内容:住所・氏名・マイナンバーなど、難しい内容はありません
まとめ|退職金は税制優遇が大きい
- ・退職金は「退職所得」として、給与よりも大きな控除と軽い課税方式が適用される
- ・「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、正しく源泉徴収される
- ・住民税は基本的にかからない
退職金は一生に何度ももらうものではありません。事前に仕組みを理解しておくと、税金面で損をせず安心して受け取れます。
③年末調整 について
年末調整とは?
会社員やパートで働いているときは、毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。しかし、給与天引きの所得税はあくまで「概算」であり、実際の税額とズレが生じることも。
そのズレを調整して正しい税額にするのが 年末調整 です。
通常は12月に会社が行ってくれますが、退職の時期によっては年末調整ができない場合があります。
退職の時期によって変わる税金の扱い
- ① 1月~11月に退職した場合
- 多くの場合、年末調整はされません。
- その年の所得税は、翌年の確定申告で精算する必要があります。
- ② 12月に退職した場合
- 会社で年末調整をしてもらえるケースが多いです。
- ただし、生命保険料控除や医療費控除などを追加で申告したい場合は、自分で確定申告が必要です。
- ③再就職した場合
- 再就職先に前職の「源泉徴収票」を提出すると、転職先の会社で年末調整をしてもらえます。
- 提出が遅れると正しく精算されないこともあるため注意しましょう。
年末調整を受けられないときはどうする?
年末調整をしてもらえなかった場合は、翌年2月16日~3月15日の期間に 確定申告 を行います。
確定申告をすると、払いすぎた所得税が戻ってくる(還付される)ことがあります。
必要な書類は以下の通りです。
- ・源泉徴収票(退職時に会社から受け取る)
- ・控除証明書(生命保険料、地震保険料、社会保険料など)
- ・医療費や寄附金の領収書(控除を受けたい場合)
まとめ|退職後は「年末調整されない」ことが多い
- 退職が 1月~11月 の場合は年末調整なし → 翌年に確定申告が必要
- 12月退職 は年末調整をしてもらえるケースが多い
- 再就職 した場合は、新しい勤務先で年末調整可能
④確定申告について
退職後、「年末調整をしていないけれど、そのままで大丈夫?」と不安になる方も多いでしょう。
会社員時代は会社が税金関係を処理してくれましたが、退職後は自分で確定申告が必要になるケースがあります。
退職後に確定申告が必要になるケース
① 年の途中で退職し、そのまま再就職していない場合
会社員は通常「年末調整」で税金が精算されますが、途中退職すると年末調整が行われません。
この場合、退職した年の所得税の過不足を確定申告で調整する必要があります。
② 再就職したが年末調整を受けられなかった場合
再就職先で年末調整をしていない場合も、確定申告が必要です。
例えば、再就職が年末に近く「年末調整に間に合わなかった」といったケースです。
③ 退職後に失業手当以外の収入がある場合
失業手当は非課税ですが、
- ・アルバイトやパート収入
- ・年金収入
- ・投資や副業収入
などがある場合は、それらを合算して確定申告が必要になることがあります。
④ 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使っていない場合)を申請したい場合
所得税の還付を受けるためには、確定申告が必須です。
確定申告の時期と方法
確定申告の期間
- 申告期間:翌年2月16日〜3月15日頃
- 還付申告なら1月から提出可能です。
確定申告の方法
- ・税務署へ直接提出
- ・郵送で提出
- ・e-Taxでオンライン提出
マイナンバーカードがあれば、自宅から手続きできるe-Taxが便利です。
確定申告の流れ
- ①源泉徴収票を受け取る
→ 退職時に会社から必ず受け取りましょう。 - ②控除証明書を用意する
→ 生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)など。 - ③確定申告書を作成する
→ 国税庁の「e-Tax」や税務署で作成可能。 - ④提出・納税
→ 還付の場合は口座に振り込み、納付の場合は期日までに支払い。
確定申告に必要な書類
退職後の確定申告では、以下の書類を準備しておきましょう。
- 源泉徴収票(退職時にもらえる)
- 支払調書や収入証明(アルバイト・副業収入がある場合)
- 控除関係の証明書
- ・社会保険料控除証明
- ・生命保険料控除証明
- ・医療費の領収書
- ・寄付金受領証明書(ふるさと納税など)
退職後の確定申告をしないとどうなる?
もし申告が必要なのに確定申告をしないと、
- ・還付金を受け取れない
- ・追加で納めるべき税金がある場合は延滞税・加算税がかかる
といったデメリットがあります。
まとめ|自分で確定申告が必要なケースがある
退職後は会社が税金を調整してくれないため、自分で確定申告が必要になるケースが多くあります。
- ・年の途中で退職して再就職していない場合
- ・年末調整が受けられなかった場合
- ・副業・年金などの収入がある場合
- ・医療費控除やふるさと納税を活用したい場合
こういったケースでは、確定申告を忘れずに行いましょう。
必要書類をそろえて、2月中旬〜3月中旬の期間内に手続きすれば安心です。
退職金には「退職所得控除」という特別な非課税枠があります。
勤務年数に応じて大きな控除額が設定されているため、退職金にはほとんど税金がかからないこともあります。
ただし、会社から「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、余分に税金が引かれることがあるため注意が必要です。
⑤退職後の雇用保険(失業給付)に課税される?
退職後の生活を支える大切な制度のひとつに 雇用保険(失業給付) があります。
ハローワークで手続きをすると、失業中の一定期間、基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
ここで気になるのが「このお金には税金がかかるの?」という点です。今回は、雇用保険の給付と課税の関係についてわかりやすく解説します。
雇用保険の基本手当は「非課税」
結論から言うと、雇用保険の失業給付(基本手当)は 所得税も住民税もかかりません。
なぜなら、雇用保険の基本手当は「生活を保障するための給付金」として扱われており、給与や事業所得のような課税対象の収入ではないからです。
そのため、受給中に税金が天引きされることもありません。
課税されない雇用保険の給付一覧
以下のような雇用保険からの給付金はすべて 非課税 です。
- ・基本手当(いわゆる失業手当)
- ・再就職手当
- ・高年齢求職者給付金
- ・教育訓練給付金
- ・就業促進定着手当
いずれも「課税所得」には含まれませんので、確定申告で申告する必要もありません。
雇用保険受給中に注意したい「税金」
雇用保険自体は非課税ですが、退職後の生活では他の税金に注意する必要があります。
① 住民税の支払いは必要
前年の収入に応じて住民税は必ず発生します。失業中でも納付書が届くので忘れずに支払いましょう。
② 健康保険・年金保険料の負担
雇用保険が非課税でも、国民健康保険料や国民年金保険料の支払いは必要です。
③ 再就職後の収入には課税される
雇用保険給付は非課税でも、再就職後の給与やアルバイト収入は課税対象です。確定申告や年末調整で整理しましょう。
まとめ|雇用保険の給付は安心して受け取れる
- ・失業給付や再就職手当など、雇用保険からの給付はすべて 非課税
- ・所得税や住民税の課税対象にはならない
- ・ただし、住民税や社会保険料は別途必要になる
⑥まとめ 退職後も「税金の管理」は忘れずに
退職すると、つい保険や転職活動に意識が向きがちですが、税金の手続きも非常に大切です。
- ・住民税の支払い方法は「普通徴収」になることが多い
- ・年末調整をしてもらえない場合は、自分で確定申告
- ・所得税を多く払っている場合は、還付される可能性あり!
源泉徴収票や控除証明書をしっかり管理して、スムーズに申告できるよう準備しておきましょう。
不明点は早めに市区町村の税務課や税務署に相談するのがおすすめです。
少し面倒でも、自分の手でしっかり管理していきましょう!
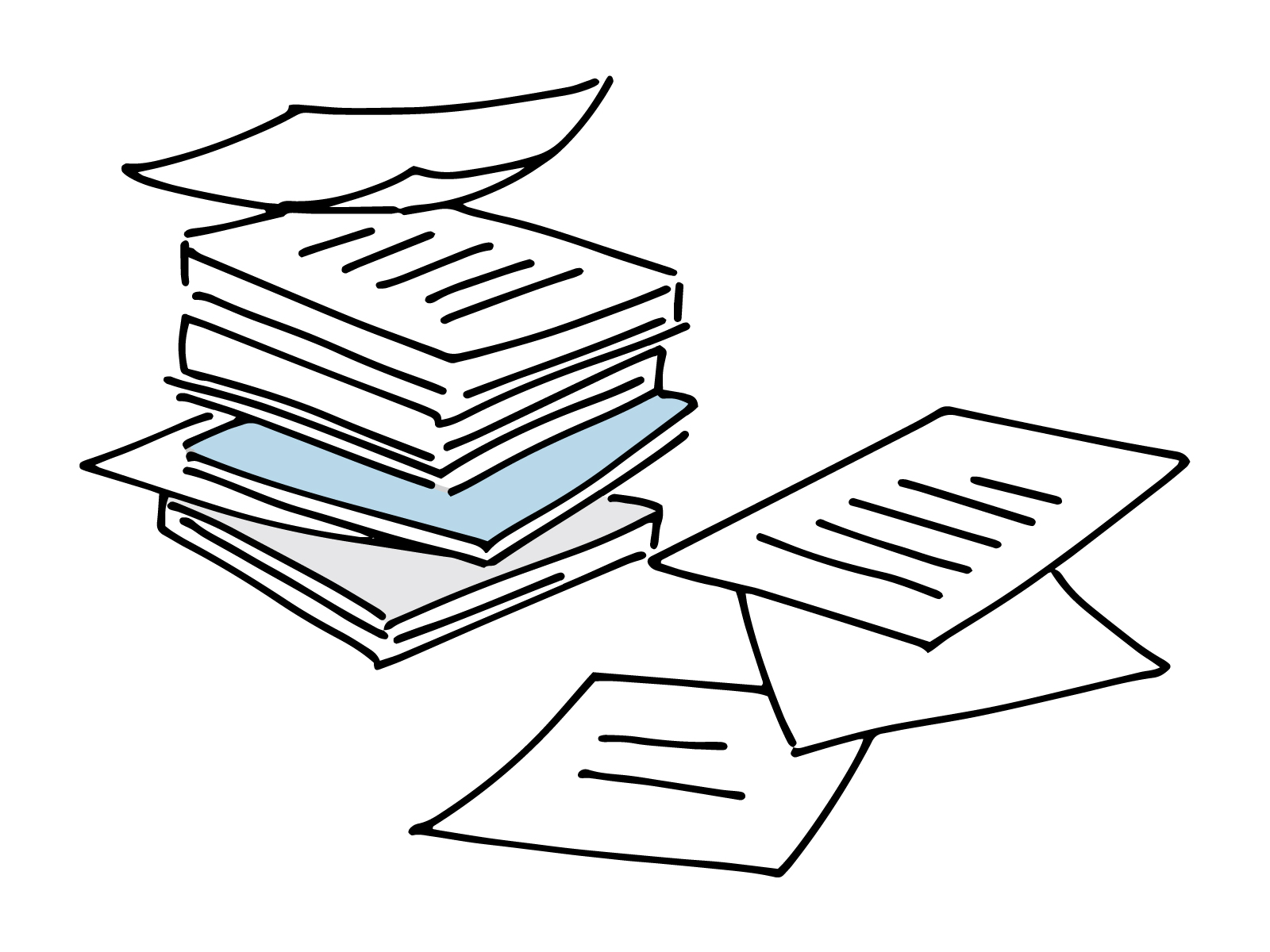
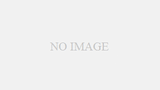

コメント